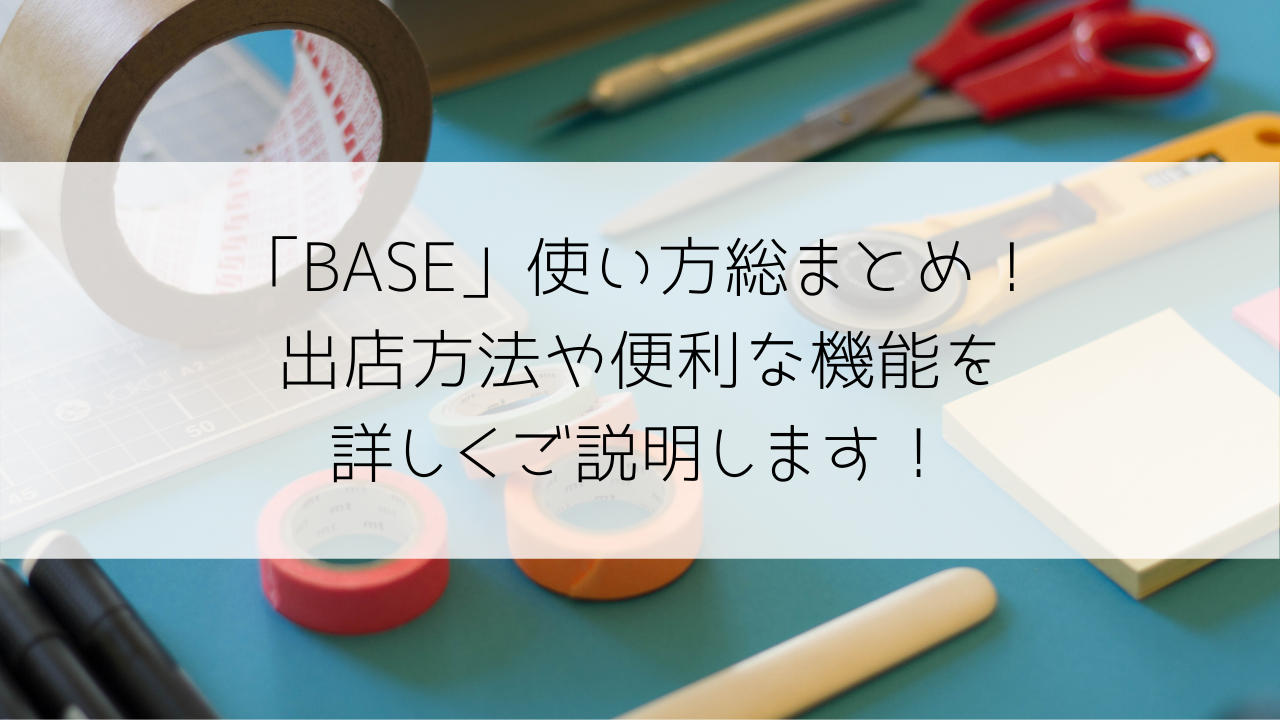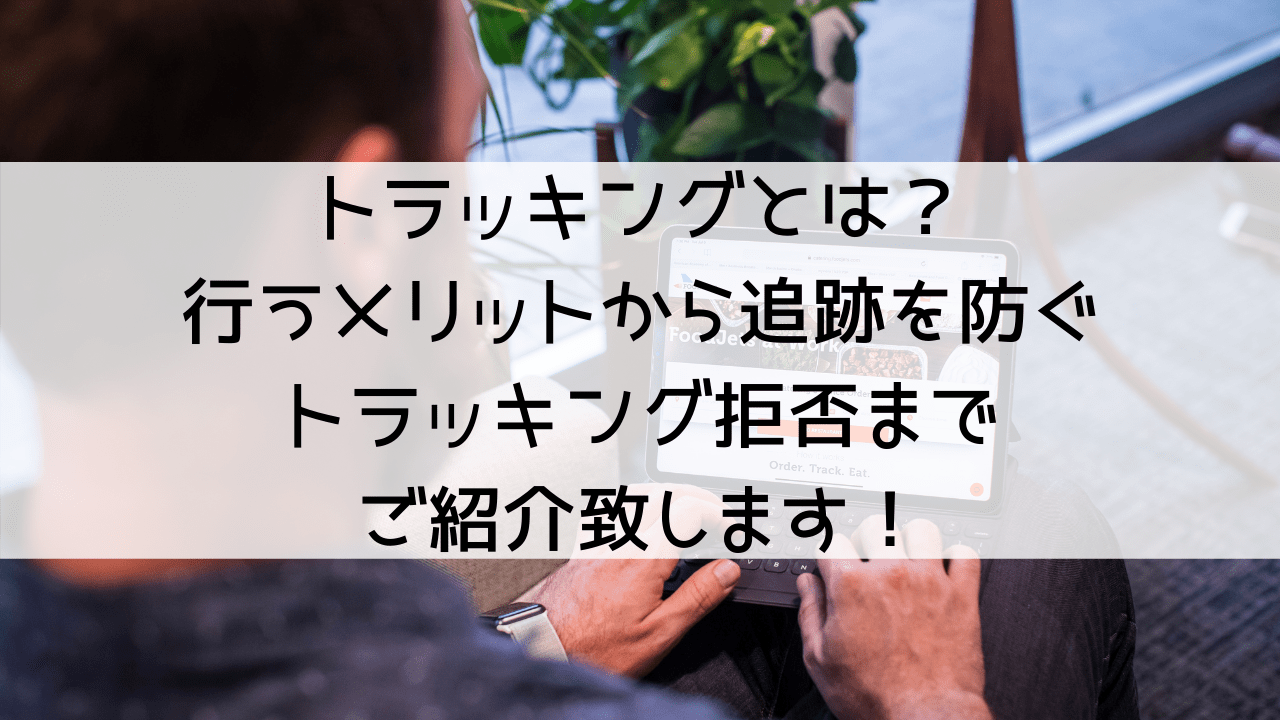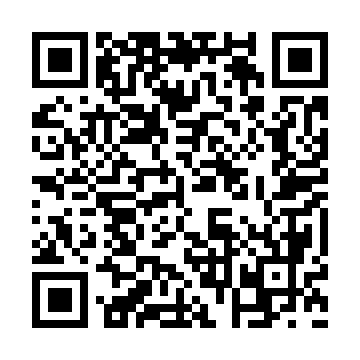Last Updated on 9月 16, 2021 by ART TRADING
越境ECサイトとは、国境を越えて取引を行う通信販売サイトを意味します。
日本国内だけでなく、世界各国でもECの市場規模は年々拡大していることから、越境ECはより注目を集めています。
今回は越境ECに関して、実際に越境ECを始める方法、成功させるためのノウハウ、アメリカ、欧州、中国、その他アジア圏など各地域におけるEC事業の特徴、越境ECで押さえるべき世界の大手ECモールをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください!
Contents
- 1 越境ECとは?クロスボーダーECとの違い
- 2 越境ECサイトを運営するメリット
- 3 越境ECサイトを運営するデメリット
- 4 国別EC市場規模ランキング
- 5 国別のECサイト特徴
- 6 越境ECで押さえるべき世界の大手ECモール
- 7 中国越境ECとは?
- 8 中国越境ECサイト売上ランキング
- 9 越境EC対応のプラットフォーム比較3選
- 10 越境ECを始めるには?
- 11 越境ECを成功させるには
- 12 日本企業が越境ECを行う際の注意点とは?
- 13 越境ECの商標を巡るトラブルとは?
- 14 越境ECは個人でも運営できる?
- 15 越境ECのニーズが高まっている理由
- 16 越境ECの日本での市場規模とは?需要は拡大している?
- 17 まとめ
- 18 関連記事
- 19 ECサイト制作ならアートトレーディング
越境ECとは?クロスボーダーECとの違い
ECサイトとは、インターネットを用いてサービスやモノの取引を行うサイトのことを意味します。その中でも、国境を越えて事業を展開するECサイトとして、越境ECとクロスボーダーECの2つがあります。
類似した意味をもつ両者の違いとして、「対象とする国の数」が挙げられます。
前者の越境ECが、ある特定の一国を対象として、EC事業を展開するのに対し、後者は、複数の国をまたがって事業を行います。そのため、日本から複数諸国に向けて商品を販売する際は、クロスボーダーECに分類されます。
2020年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、これから世界中でのEC需要は高まる一方であると予想されていることから、両者とも目が離せないキーワードとなっています。
越境ECサイトを運営するメリット
越境ECサイトを運営するメリットをご紹介します。
①商圏の拡大
越境ECサイトにて販売を行うことで、「ネット環境さえあれば販売可能」というECサイトで販売を行う最大のメリットをさらに活かすことができます。
とくに、少子高齢化や人口減少により、日本国内の市場は成熟期を迎えているといわれ、多くの新規顧客獲得を見込めないという現状があります。そこで、越境ECサイトを構築することで、日本にいながら、これから成長が見込める市場にて、販売活動を実施できるというメリットがあります。
②初期費用の大幅な削減
日本企業またはブランドの海外進出における従来の方法としては、海外の展示会に出店して仲介業者と出会ったり、実店舗をもって出店または出品したりすることが主流でした。しかしながら、EC事業拡大に伴い、インターネットショッピングが世界的に普及したことで、実店舗をもたなくても海外への販路拡大を図ることができるようになりました。
越境ECサイトでは、設備費や人件費、テナント代などの初期費用だけでなく、販売員育成のためのマニュアル作成や浸透などの作業工程を削減することも可能で、海外進出のハードルが以前よりも低くなっているといえるでしょう。
越境ECサイトを運営するデメリット
①販売先の国それぞれに合わせた対応が必要となる
越境ECサイトにて、複数の国での販売を図る際には、「翻訳」「決済」「発送・配送」など、物流過程で発生する業務を、それぞれの国に合わせて適応させる必要があります。とくに、言語の壁が問題となり、商品の魅力を十分に伝えられなかったり、柔軟にお客様対応を実施できないという懸念点も挙げられます。そのため、翻訳などのサポート体制をしっかりと整える必要があります。
さらに、物流業務に加えて見逃すことのできない点が「法律」です。国によっては、ECサイトを開設する時点で、ライセンスの取得が必要となる場合もあります。
進出を企画する時点で、これら4つの点に関して、どのような対応が必要になるのか、入念に確認するようにしましょう。
②関税などの規制が増える
国内EC業務との大きな違いとして、関税や国際輸送に関する規制などが挙げられます。関税の手続きに関しては、法律などと同様に各国の決まりがあり、国によって輸出入できるもの、できないものが異なります。専門的な知識が必要となる部分でもあるため、アウトソーシングサービスを利用して、外部のプロに委託するケースも多くみられます。
③配送料や手数料が高い
越境EC事業では、国内ECと比較して、配送距離が長く、手続きも増えるため、配送料や手数料など、ユーザーが負担するコストが高くなってしまいます。よりコストがかかってしまう越境ECだからこそ、いかに商品そのもので顧客を魅了できるかという、商品価値の高さがより問われるようになります。
国別EC市場規模ランキング
経済産業省の調査による、世界のBtoC市場規模のランキングは以下の通りです。
参照:)報告書
国別のECサイト特徴
それでは自社の商品を海外販売事業に参入させたいと考えた時、どんな事を考えるといいのでしょうか。国別に課題や注意点をまとめてみましょう。
米国・欧州
米国には2大大手通販サイトである、Amazon、eBayが普及しており、通販先進国であります。また、米国・欧州では日本製品に対して強いブランド力を感じてくれる国でもあり、日本製の商品価値を提供する機会は多く存在します。
返品や交換率も低いため、越境EC初心者にも向いており、まずは米国・欧州をターゲットに…と海外販売事業を開始する方も少なくありません。
この様に初心者が歓迎される反面、競争率も高く様々な工夫が必要です。
商品紹介動画をYoutubeにアップロードしたり、Facebookへ広告を打ったりあらゆる主流のSNSを使う必要があります。またサイトのビジュアルも大切で、言語を使わなくても伝わる様な商品写真には色鮮やかさであったり、統一感など色々な視点からとことんこだわるべきです。
中国
中国もまたEC市場が大きく、2大大手通販サイトである天猫国際と京東全球購への出店が主流となっています。
独自ドメインの場合政府の監視があるため表示されなかったり表示速度が一気に遅くなることもあります。政府が監視するグレートファイヤーウォールとは万里の長城に例えて名付けられており、
ディスニーキャラクターの『くまのプーさん』も閲覧制限対象となっているほど、審査基準ハードルは高く設定されています。しかし、香港とマカオに関しては中国本土の法律が定められていないので、管理外となっています。
また、中国では知的財産権などの権利保護に注意しなくてはいけないので、現地パートナーと委託して、独自のルールをインプットし、リスク回避していく必要があります。やり方によっては膨大な顧客数の期待が考えられる中国市場ですので、専門情報正確なルートで取得しておくといいでしょう。
その他アジア圏
台湾や香港ではECリテラシーも高く、日本製品にも注目している顧客が多いため、出店するEC事業者も増えています。
日本発信で台湾や香港に越境EC出店を可能とするプラットフォームも増えてきているため、導入もしやすくなっています。
シンガポール、マレーシアでは価格競争力が必要となり、タイにおいてはEC普及率はそこまで高くありません。
出品したい商品が海外企画の家電の場合は国によっては国際認証を必要とするので注意しましょう。
越境ECで押さえるべき世界の大手ECモール
メルカリ(mercari)
メルカリは日本でスタートアップしたCtoC向けの「フリマアプリ」です。2014年9月に米国に進出し、わずか1年8ヵ月の期間で米国国内では1000万ダウンロードを突破しています。
メルカリでは他に海外展開しているヤフオクなどに比べて出店ハードルが低いこともあり、米国国内では都市部の人のみでなく郊外に住む人にも多く使用されています。
<アメリカ>Amazon.com
Amazon.comは、アメリカ・ワシントン州・シアトルに本社を構えるアメリカ最大のECモールです。日本でも認知度が高く、Yahoo!ショッピングや楽天市場などと並んで、幅広く利用されています。取り扱う商材は多岐にわたり、2018年には、全世界の有料会員が1億人を突破した、世界で最も有名な越境ECモールといえるでしょう。
また、アメリカに加え、イギリスやドイツ、フランス、カナダ、インドにおける越境ECモールでも国内最大のシェアを占めています。
<アメリカ> eBay
eBayとはアメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を構えるアメリカ合衆国の大手グローバルEC企業で、世界中にユーザーを持っています。
特徴としてはオークションサイトであるという事で、日本で言うヤフオクのようなサイトとなっています。eBayの魅力はなんと言っても市場規模の大きさとユーザーの多様性や数の多さですが、その反面競合性は高いので商品出品における工夫は問われます。
扱っている商材も多種多様ですが、出品禁止商品などもあるので、詳しくはeBayポリシーをご参照ください。
<インド>Amazon・インディア(Amazon.India)
インド越境EC市場では、世界でシェアを伸ばすAmazon Indiaが大変注目されています。
インドは世界第2位の多さとなる13億人もの人口を抱えており、今後は巨大な消費市場として成長していくことが期待されています。
加えてインドでは人口の半数が24歳以下で、市場自体が若いという点も大きな魅力です。
<韓国>G-Market
G-Marketは、電子商取引事業を中心に展開するe Bay Korea社が運営する、韓国最大級のECモールです。韓国語の他に英語、中国語にも対応しているため、韓国在住のユーザー以外にもアプローチし得るという強みを有します。アパレルや美容系、食品など、商材は多岐にわたります。
G-Marketの最大の特徴として、楽天市場との協業が挙げられます。そのため、韓国EC市場により気軽に参入できるようになりました。
<ドイツ>Otto
Ottoは、世界最大級のオンラインリテーラーが運営する、ドイツ2番手の越境ECモールです。ドイツ国内にて、最大シェアを誇るECモールは、Amazon.comですが、Ottoはアパレルやライフスタイル分野で強みをもちます。ドイツをはじめとして、イギリスやフランスなどヨーロッパの幅広い国々の消費者へのアプローチが可能です。
<フランス>Cdiscount
Cdiscountは、EC事業を展開するCnovaが運営する、フランス2番手の越境ECモールです。ドイツ同様、フランス国内でのシェアno.1は、Amazon.comですが、僅差でCdiscountは2位に位置します。書籍やDVD、家電や電子機器、雑貨などが主な商材で、フランスや日本以外でも、中国や香港の企業の出店が多くみられます。
<ブラジル>Mercado Libre
Mercado Libreは、EC事業を主軸とするEmporio Comprasが運営する、南米最大のECモールです。なかでも、ブラジルでの売上が南米トップを占め、ブラジル国内のECモールでの最大シェアを誇っています。取り扱う商品は幅広く、もともと中古品を扱っていたという背景から、中古品の出品も多くみられます。
<香港>HKTVmall(網上購物)
HKTVmallは、香港の通信系企業City Telecomが運営する、香港在住のユーザーに向けたECモールです。香港最大級のECモールで、食品や日用品を主軸とし、その他美容関連や家電製品も取り扱っています。
<台湾>PChome/PChome商店街
PChomeは、EC事業を行う運営者(PChome)による、台湾最大級のECサイトです。越境ECモール事業を行うPChome商店街は、出店数12万店舗以上、アイテム数4億点以上を取り扱っています。
中国越境ECとは?
中国越境EC市場は世界でも有数の巨大市場です。中国越境EC市場は2018年の3兆2000億円から2022年には5兆3000億円までに拡大さると言われています。このように市場が大きいという点が特徴の中国越境ECです。しかし、中国越境ECは法律の面で厳しい面があるため実際に出店する際には注意が必要です。
中国越境ECサイト売上ランキング
今回は、以上の国々におけるおすすめECモールをそれぞれご紹介します。
1位:天猫国際(Tmall Global)
天猫(Tmall)は、アリババグループが運営する、中国のECモールで、日本語では「テンマオ」と呼びます。天猫は、中国のECサイト市場の約60%を占め、取引額は48兆円以上に登る、圧倒的な存在感を誇ります。
高級ブランドや、世界的に知名度且つ信頼性の高いブランドや商品を扱っており、天猫国際では、海外事業者が出店できるサービスを提供しています。
2位:京東商城(JD.com)
大手ECサイトプラットフォーム企業の京東集団が運営する京東商城は、中国のECモールで第2位のシェア率を誇る越境ECサイトです。2015年6月には、日本製品専門サイトの「日本館」をオープンしたこともあり、中国の越境EC市場に乗り出そうとしている日本企業の誘致に力を入れている点が特徴の1つです。
3位:唯品会(vip.com)
唯品会は2008年中国・広東省広州市で設立され、2012年には中国市場におけるアクセサリー・アパレルのジャンルで4位に輝くなど、急成長を遂げている企業です。女性顧客を中心に中国で2億人の会員を有しています。
越境EC対応のプラットフォーム比較3選
つづいて、日本をベースに越境EC事業を開設できるECモール・カートシステムをご紹介します。
Shopify
ShopifyはカナダのShopify社がEコマース用に構築したプラットフォームです。
ECサイト開発や運営を助けてくれるプラットフォームであり、様々な機能をアプリを使って追加していく事ができます。このアプリがShopifyの魅力の一つでもあり、とにかく充実した種類が用意されています。中でも翻訳アプリは人気があり、越境ECサイトならではの言語の壁を乗り越えるための一助になってくれます。
Magento
MagentoはAdobeが提供しているECプラットフォームで、2017年時点での世界におけるシェアは2位に輝くなど日本よりも世界で広く浸透しています。そのため、越境ECにぴったりのECプラットフォームと言えます。PHPというプログラミング言語を使用するため知識がなければ構築するのは難しいですが、知識があれば、独自性の高いECサイトを作成することができます。
Wix
Wixはイスラエルで生まれたECプラットフォームです。WIxではデザインや機能が多数用意されており、プログラミングの知識がなくてもパーツやデザインを組み合わせて思い通りにECサイトを構築することができます。
越境ECを始めるには?
実際に越境ECを始めるとなった際は、具体的に何から始めれば良いのでしょうか?
①商品を準備する
越境ECを始めるとなった際はまず商品を準備します。日本で需要があったとしても、現地では需要がない場合があります。商品を準備すると同時にその商品は現地でニーズがあるのかのリサーチも必要です。
②法律や規制を確認する
中国など、現地の法律や規制が厳しい国は多くあります。また、厳しいだけでなく、頻繁に法律や規制が改定される国もあります。事前に調べてトラブルにならないように気をつけましょう。
越境ECサイトを開設する際の4つの手段を、特徴やメリット・デメリットを踏まえてご紹介します。
③出店方法を選択する
越境ECの出店方法は大きく分けて4つあります。
Ⅰ.海外のサーバーを利用して自社ECサイトを開設する
進出を図る国のサーバーを借りて、自社でページの作成を行います。メリットとしては、現地企業やブランドと同じフィールドにたつことができる点が挙げられます。一方で、現地企業と同等レベルで、該当国の言語や規制などを考慮・理解しなければならないというハードルの高さも挙げられます。そのため、該当の国への本格的な参入を目指す事業者におすすめです。
Ⅱ.海外のECモールに出店する
海外の企業が運営する大型ショッピングモールに出店することで、販売を行います。メリットとしては、すでに高い集客力のある場で販売できることが挙げられます。デメリットとしては、「手数料が高いこと」「日本語を使えないこと」が挙げられます。そのため、ある程度言語を使いこなすことのできる人材や環境が整っている事業者におすすめです。
Ⅲ.日本国内のサーバーを利用して自社サイトを開設する
日本国内のサーバーを借りて、自社でページの作成を行います。メリットとしては、言語の壁がなく、規制に関する豊富な知識を有しているという点が挙げられます。デメリットとしては、海外消費者に向けたブランド構築には、多くの時間と労力がかかってしまうことが挙げられます。そのため、自社の越境ECサイト構築を試みる時点で、既に一定数の認知度がある事業者におすすめです。
Ⅳ.海外対応の国内ECモールに出店する
日本語対応の国内ECモールの中でも、海外への拡販に対応したショッピングモールを利用することで、販売を行います。メリットとしては、集客力の高さに加え、日本語ですべて行うことができるため、手厚いサポートが受けられることが挙げられます。デメリットとして、手数料の高さが挙げられます。そのため、越境ECサイトへの参入手段として利用されることが多いです。
越境ECを成功させるには
上記にあるようにターゲット理想国にしたい国に対する知識を充分取り入れなくてはならないと同時に、自社の商品特製がどの国に適合するかダブルチェックする必要があります。
戦略設計と分析こそ成功のカギと言えます。
また、投資額や撤退時期についても独自の判断基準が必要です。戦略設計においてのみ、越境EC特化型コンサルに相談することもおすすめします。展開期間は最低でも3〜5年の長期スパンで考えないと成果は出ないと言っても過言ではありません。撤退時期を早まってしまってもよくないので、常に気長に構える姿勢でいましょう。
また、各国の言語が喋れるまたは扱えるだけの人に任せっきりになってしまってもよくありません。
グローバル且、為替などを含める随時変動する経済状況に目を向けれる人材こそが越境EC運営担当者に適しています。
トライアンドエラーを何度も繰り返し、成功するまで楽しめるという覚悟で事業展開する事をおすすめします。
日本企業が越境ECを行う際の注意点とは?
インターネットさえあれば、国内でも商圏を拡大できるなどと行った、大きな可能性を秘めた越境ECですが、実際に越境EC事業に取り組む際には、リスクや課題も念頭に置く必要があるでしょう。
越境ECが抱えるリスクや課題は以下の4点です。
インターネットさえあれば、国内でも商圏を拡大できるなどと行った、大きな可能性を秘めた越境ECですが、実際に越境EC事業に取り組む際には、リスクや課題も念頭に置く必要があるでしょう。
越境ECが抱えるリスクや課題は以下の3点です。
課題1. 言語の壁がある
海外発信を考える際に真っ先に思い浮かぶ弊害が言語の壁であります。
英語圏内ならまだしも他の言語に対しての教育の場は少なく、Google翻訳等翻訳機能を駆使したところで限界は見えています。しかし最近の越境EC対応プラットフォームにはその様な言語の壁を解消させてくれる様なアプリやプラグインの導入がされており、日本語しか扱えない事業者の海外展開も叶える事ができるのです。
しかし、商品の細かいニュアンスや魅力は文化の差を考慮しなくてはいけないため、限られたリソースの中での対応力を課題と考える事もできます。
解決策
まず対象国を決めたら、その国のネイティブスピーカーへのアウトソースも視野に入れておきましょう。翻訳代行サービスという選択肢や越境ECに特化した運用代行サービスの利用も効果的です。
課題2. 関税などの取引規制が多い
国際輸送における国や商品毎の手続きは多種多様でなかなか想定できない手続きを必要とします。
全ての事象における通関を把握しなくてはいけないため、国際輸送に関する勉強は必須です。
国によっては輸送できない商品があるため、商品登録も各商品毎に検討しましょう。
また、なるべく返品・交換トラブルなどを起こさないためにも、梱包には最新の注意を払う必要があります。
解決策
販売する商品がどの国に適応しているかどうかはSNSを利用したリサーチも効果的です。
調査専門業者を介して情報を入手する方法もあります。
課題3. 決済方法・為替変動がある
国によって通貨が違うと同様に主流の支払い方法にも差があります。
米国・欧州がターゲットであれば、Paypalの導入は必須ですし、中国であればAlipayやWechatPayも導入しなくてはいけません。
また為替変動に応じた売上金額への影響を受ける事になり、他国通貨での表記に関しては色々な世界経済事情が絡んできます。
日本円での表記にして日本の為替に合わせてもらうのか、他国の為替を随時チェックするのか、
リスクの選択を誤らないようにしましょう。
解決策
対象国の主流決済方法は何がなんでも導入しましょう。
希望する決済方法がないサイトでの購買意欲は削がれ、離脱率は圧倒的に増えてしまいます。
為替に関して心配な方はまずは日本円で設定する事をおすすめします。
課題4.配送料や手数料が国内ECよりも高額
越境ECサイトの場合、インターネットサイトを通じて注文があった商品は日本から海外へ輸出するという形で商品を発送することになります。
配送の物理的な距離が長くなる分、それに必要な配送料や手数料は日本国内よりも高額になります。そのため結果としてユーザーが負担する金額は高額になる傾向にあります。
このことから国内のECサイトで行うような「低価格」や「お得」を売りにした販売戦略の導入は難しいことが多いです。
解決策
「価格」を軸に置いた販売戦略を行うことは難しいので、それよりも外国人に人気のある日本の商品やブランド、海外にはない珍しい商品を扱うなど商品自体の価値を重視して越境ECサイトの運営を行うことをおすすめします。
越境ECの商標を巡るトラブルとは?
日本における越境EC市場では、同じく越境ECの栄えている中国・米国と比べて日本企業の商標権意識が低いことから商標権に関するトラブルが相次いでいることが問題となっています。
実際にコトボックスが2021年3月に行った「越境EC事業における商標に関する実態調査」によれば、越境ECで自社ブランドの海外販売を行う際に販売する国での商標を慈善ン位申請しなかったEC事業者は66.4%に上っている。
加えてこちらの調査では、販売する国で商標申請をしなかったばかりに「現地会社から商標を取られた」や「商標問題で海外から撤退することになった」といいう事例も明らかになっています。
これらのことから日本の企業が越境ECで海外に自社ブランドを展開する際には、販売する国で商標を事前に申請することは非常に重要なステップであることが分かります。
越境ECは個人でも運営できる?
越境ECは国内でのEC事業に比べて規模が大きいので、個人で行うケースは稀ですがCtoCビジネスとして越境ECの運用を行うことは十分可能です。
越境ECの基本的な運用方法は国内ECと同じですが、越境ECは国内ECと比べて競合が少ないため、取り扱う商品やブランディングをしっかりと行っていけば個人でも成功することのできる市場のようです。
越境ECのニーズが高まっている理由
越境ECのニーズが高まっている理由には以下の2点があげられます。
・スマートフォンの一般化
・訪日外国人による商品購入
ここでは、越境ECのニーズが高まっているそれぞれの理由について詳しくご説明していきます。
スマートフォンの一般化
越境ECのニーズが高まっている1つの要因として、スマートフォンというインターネットに簡単にアクセスできる機器の普及があげられます。
スマートフォンの端末が比較的安価で手に入るようになったこともあり、世界中の多くの国ではスマートフォンから手軽に海外のECサイトにアクセスすることも可能になりました。
多くの人びとにとって自分で海外のECサイトにアクセスし、自国商品などと比較をしながらより低価格で高品質なものを購入することが一般的となっています。
加えて自宅の近くにショッピングモールなどがない地域に住んでいる人も手軽にスマートフォンを経由して海外の商品を購入できるようになったことも越境ECサイトのニーズが高まっている理由としてあげられます。
訪日外国人によるリピート購入
越境ECのニーズが高まっているもう1つ要因として、訪日外国人が日本を訪れた時に購入した商品を気に入り、自国に戻った後でも日本の越境ECサイトから商品をリピートして購入しているという点があげられます。
また、1度も日本を訪れたことのない人でもWEBサイトで商品を知ったことがきっかけで日本の商品を購入することがあります。そのようなときでも越境ECでは簡単に商品にリーチすることができます。
越境ECの日本での市場規模とは?需要は拡大している?
越境ECの市場は年々増加傾向にあります。
経済産業省の実施した「電子商取引に関する市場調査について」という報告書によると、日本・米国・中国の3か国間における越境ECの市場規模は、前年と比べていずれの国でも増加していると述べられています。
特に中国消費者による日本のEC事業者からの越境EC購入額は1兆6558億円で、前年から7.9%と大きく増加しています。中国消費者による日本の越境EC市場の拡大傾向は、2018年のデータからも読み取ることができます。
経済産業省が発表した「電子商取引に関する市場調査について」の2018年版によると、中国消費者による日本のEC事業者からの越境EC購入額は1兆5345億円で、前年から18.2%増加しています。
このような傾向から、日本の越境EC市場では中国消費者のニーズへの注目が集まっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。越境ECは、言語の壁や複雑に思える規制、法律などにより参入が困難だと思われがちです。しかしながら、実店舗での進出と比較して、より手軽に新規顧客獲得を図ることができます。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事
・ネットショップ・EC運営代行とは?仕事内容や費用、格安代行会社も含めてご紹介!
・ECサイト売上アップのための改善施策をご紹介!CVRやUIの改善点も詳しく解説します
・【2020】国内外のShopify(ショピファイ)導入事例をまとめてみました!導入メリット・デメリットもご紹介
ECサイト制作ならアートトレーディング
世界170か国以上のNo.1シェアを誇るグローバルECプラットフォーム「shopify」を導入した自社ECサイト制作をご提案いたします!
当社は、10年以上の実績・100社以上のECサイト構築運用 経験でお客様のお悩みを解決してまいりました。
新規のECサイト制作、既存サイトからの移転・乗り替えだけでなく、運営代行・コンサルティング・在庫連携・物流まで幅広くサポートが可能です。
EC支援といってもお客様の状況はさまざまです。これからECサイトを展開したい、サイトはあるが販売促進のノウハウが欲しい、スタッフが足りなくて人手が欲しい等々…。
現在の状況を分析し、ニーズに合った提案を行い、実践し、ECサイトだけでなくお客様ともども成長していただけるような支援を行います。